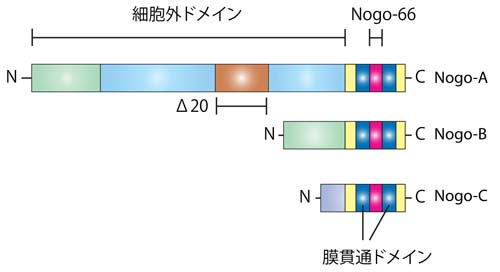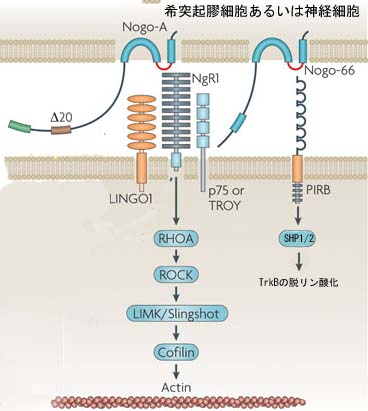Nogo
(読み方)ノゴ (英)Nogo
概要
Nogoは脊椎動物の中枢神経の軸索伸長の阻害効果をもち、軸索損傷後の再生を阻害する分子であると考えられている。Nogo-A蛋白内には2つの軸索伸張阻害作用を有する蛋白ドメインがあり(Δ20とNogo-66)、軸索伸長阻害のみならず、軸索の先端の成長円錐を虚脱させる作用を持っている。動物実験によりNogo-Aあるいはその下流のシグナルを阻害することにより、神経損傷時における神経軸索の再生を促すことが示されてきた。このことから軸索が損傷を受け、その再生ができないことにより重度の後遺障害が残る脊髄損傷や多発性硬化症のような脱髄疾患における軸索再生治療への期待がかけられている。また、病態時のみならず、脳内の学習と記憶のプロセスを強化する課程において重要な役割を果たすことが分かっている。
発見の歴史
研究の萌芽
今からおよそ80年前に、スペインの神経学者Ramon y Cajalが再生阻害の謎を解く重要なヒントを見いだした[1]。Cajalは、感覚を伝える後根神経という末梢神経の軸索を切断し、その後の軸索の再生を観察した。再生しかけた軸索は、脊髄の中に侵入できず、再生できなかった。その後、Aguayoらは、脊髄の損傷による欠損部を末梢神経の周囲組織をグラフトとして移植することで、このグラフト内を軸索が再生する結果を得た[2]。これらにより、神経細胞自体に再生する力がないのではなく、神経細胞を取り巻く環境が再生に適していないのではないかと考えられるようになった。
1980年代、更に研究が進展し、ミエリンが神経突起の伸展を抑制することが報告された。そして、Schwabらは、ミエリンの中に再生を阻害している分子が存在していると考え、ミエリンの各フラクションに対する抗体を作成した。In vitroの実験により、IN-1抗体はミエリンの作用を中和し、220 kDaの糖蛋白に結合することが判明した。また、IN-1抗体を脊髄損傷させたラットに投与すると、軸索再生と運動機能の回復が認められた[3]。これら一連の成果により、軸索再生阻害という概念が実在のものとして信じられるようになった。しかし再生阻害を担う蛋白の単離は10年かかっても実現しなかった。
Nogoとその受容体の発見
Schwabのグループは1999年に、IN-1抗体の認識する蛋白の部分配列を公開した[4]。このペプチド配列をもとに、長年捜し求めた目的の蛋白がクローニングされ、3つのグループによって同時に報告された[5][6][7]。Nogoと名付けられたこの蛋白はその配列情報から2回膜貫通構造をもっていると考えられ、培養神経細胞に対して突起伸展抑制作用をもっていた。Nogoは選択的スプライシングによって3つの長さの異なる蛋白が作られる。このうち最も長いNogo-Aには再生阻害に働く2つのドメインが存在する。Schwabらはアミノ端のNogoがより重要であると考えているが、Strittmatterらは膜貫通領域に囲まれる66個のアミノ酸からなるペプチド部分(Nogo-66)の再生抑制作用に注目し研究が進められた。
そして、Nogoの神経細胞上の受容体が同定された。StrittmatterらはNogo-66の受容体NgR1を同定した[8]。NgR1は細胞内ドメインをもたないGPIアンカー型蛋白であり、Nogo-66に対し高親和性を示すことが分かった。
蛋白の一次構造とドメイン
図1に示されるとおり、Nogo蛋白の一次構造は、RTN4遺伝子によりコードされる二回膜貫通型の蛋白である。 RTN4遺伝子からは、3つのアイソフォームNogo-A,Nogo-B,Nogo-Cが作られる。軸索阻害作用を持つNogo-66はNogo-A,-B,-Cに共通のドメインである。一方、Δ20ドメインは、Nogo-Aのみが持つことが分かっている。
二回膜貫通型ではあるが、図2で示されるように、アミノ末端部は、細胞外に露出していると考えられている。
蛋白の機能
成体神経細胞に対する軸索伸展阻害作用
受容体と細胞内シグナル
Nogo受容体はGPIアンカー型蛋白であり、細胞内ドメインを持っていない。したがってNogo受容体は神経細胞内にシグナルを伝達することができないため、シグナル伝達を担う別の受容体がNogo受容体と共受容体を形成しているのではないかと考えられた。
その頃、山下(現大阪大学教授)らは機能の良く分かっていなかった神経栄養因子の受容体であるp75受容体の発生時にける役割を明らかにした。p75は、主として末梢神経の軸索伸展を促進していることが報告された[9]。その後、山下等はこのp75が軸索伸展阻害因子の一つMAG(Myelin Associated Glycoprotein)のシグナルを神経細胞に伝える受容体であることを見い出した[10]。P75を欠失しているマウスの神経細胞はMAGに対する反応性を失ったのである。
p75がMAGのシグナルを伝える因子であれば、p75とNogo受容体は共受容体を形成し、MAGのみならずNogoとOMgpのシグナルも伝えていることが予測される。その仮説は直ちに検証され、Heらによって正しいことが証明された[11]。こうしてp75は再生阻害のキープレーヤーであると考えられるようになった。
それではp75を介してどのような細胞内シグナルが形成されるのだろうか。 ニューロトロフィンがp75に作用して軸索の伸展を促すメカニズムは、Rhoの不活性化である[12]。Rhoはアクチン骨格系あるいはチューブリンを制御することによって、細胞の形態形成の鍵となる蛋白である(図5)。Rhoがミエリン由来蛋白の効果に関わっているだろうとは以前から予想されていた。Rhoを不活性化するボツリヌス毒C3により、ミエリンの再生阻害作用は消失する。事実MAGにより神経細胞内でRhoが活性化されることが証明された21)。さらにメカニズム解析がなされ、p75によりRhoとRhoの活性化阻害蛋白であるRho guanine nucleotide dissociation inhibitor(Rho GDI)が解離することでRhoが活性化に導かれる事実が判明した23)。
しかしながらp75/Nogo受容体のみでは、ある種の細胞ではリガンドで刺激してもRhoが活性化しない。必要ではあるが十分ではないということである。そこでLingo-1が新しいp75/Nogo受容体コンポーネントの仲間入りした24)。この受容体がどのようにシグナル伝達に関わっているかについては明らかではないが、p75/Nogo受容体/Lingo-1という受容体複合によりRhoが活性化されて、軸索伸展が阻止されるという基本モデルが完成した(図5)。
Nogoは本当に再生阻害因子か?
ここまでの急速な研究の発展により、中枢神経がなぜ再生しないのかという疑問に分子の言葉で答えられるようになったと多くの研究者が考えた。しかしながら、最近になってこの単純なモデルの一つ一つが検証され、再検討されなければならない問題が浮上してきている。
疑問はTessier-Lavigneのグループから提示された25)。彼等はNogo受容体のノックアウトマウスを作成し、その神経細胞を用いて、軸索再生の実験をin vitroで行った。神経細胞はワイルドタイプと同様に、ミエリンのみならずNogo-66によって突起の伸展阻害がおこったのである。これに対して、P75ノックアウトマウスの神経細胞はNogo-66に不応性であることが再度確認された。以上の結果が正しいとすると、p75はミエリン由来因子の受容体であるが、Nogo受容体はそうではないということになる。従ってNogo受容体に集約されるというモデルは今後再検討されなければならない。
2. Nogoは再生阻害蛋白か?
Nogoのノックアウトマウスを3つのグループが独自に作成し、脊髄損傷後の再生を評価した26,27,28)。しかしその結果は食い違っていた。Strittmatterらは、ノックアウトマウスでは再生は促進され、運動機能の回復も良かったと報告した。Tessier-Lavigneらは、再生は認められなかったと断じ、Schwabは軽度の再生線維と芽生え現象を確認した。3つのトップグループがそれぞれ異なった結果を報告した理由は今もって解明されていない。しかしNogo以外にも複数の再生阻害因子が存在することを考慮すると、微妙な実験方法の違いによって結果がぶれることも考えられる。マウスで脊髄損傷を作成するというのは、極めて困難な技術であることも影響しているかもしれない29)。
3. ミエリン由来因子はin vivoで再生阻害に働いているのか?
3つの因子のシグナルを止める方法として、p75が考えられる。P75ノックアウトマウスを用いて、再生が評価された。しかしながらこのマウスで再生は認められなかったのである29)。
in vitroではp75はシグナル伝達因子として働いているが、in vitroで使用する細胞はin vivoにおいて重要な神経ではない。例えば大人の皮質脊髄路を形成する大脳皮質ニューロンを培養してin vitroで使うことはない。大人においてはもっと別の受容体がシグナルを伝えている可能性がある。
この仮説から出発し、p75のファミリー蛋白であるTroyがもう一つのシグナル伝達因子として機能していることをHeらとMiらのグループが最近報告した(図6)30,31)。Troyは成体の脳でも高い発現を示す。それでは、Troyのノックアウトマウスは脊髄損傷から回復できるかどうかについて検討されなければならないだろう。
Ⅴ シグナル制御による神経軸索再生への取り組み
再生阻害蛋白は3つ見つかっているが、4つ目が存在する可能性はある。それならば未知の因子を探索したり、その受容体を追うよりは、再生阻害の共通のシグナルというものが存在するならば、そこをブロックすることで生体での軸索再生が実現できるはずである。最近研究者が注目しているのはRhoおよびその下流の因子であるRho kinaseである。脊髄損傷させたラットにRhoの阻害剤であるC3あるいはRho kinase 阻害剤を局所投与することにより、神経症状の改善ならびに軸索再生が促進されることが、複数のグループによって確認されている32,33,34)。これが現時点で有効な方法であると考えられる。
その他の機能
胎生期神経前駆細胞の放射状移動を制御
Critical periodの形成に関わり、成体の軸索の再編成を制御し、神経ネットワークの可塑性を制御
βセクレターゼ活性の制御によるAPPの切断を制御
- ↑ Ramon y Cajal, S. Degeneration and regeneration of the nervous system. Hafner, New York, 1928.
- ↑
David, S., & Aguayo, A.J. (1981).
Axonal elongation into peripheral nervous system "bridges" after central nervous system injury in adult rats. Science (New York, N.Y.), 214(4523), 931-3. [PubMed:6171034] [WorldCat] [DOI] - ↑
Schnell, L., & Schwab, M.E. (1990).
Axonal regeneration in the rat spinal cord produced by an antibody against myelin-associated neurite growth inhibitors. Nature, 343(6255), 269-72. [PubMed:2300171] [WorldCat] [DOI] - ↑ Spillmann, A.A.: J. Biol. Chem., 273, 19283-19293 (1999)
- ↑ Chen, M.S., et al.: Nature, 403, 434-438 (2000)
- ↑ Grandpre, T., Nakamura, F., Vartanian, T., Strittmatter, S.M.: Nature, 403, 439-444 (2000)
- ↑ Prinjha, R., et al.: Nature, 403, 383-384 (2000)
- ↑ Fournier, A.E., et al.: Nature, 409, 341-346 (2001)
- ↑ Yamashita, T., Tucker, K.L., Barde, Y.A.: Neuron, 24: 585-593 (1999)
- ↑ Yamashita, T., Higuchi, H., Tohyama, M.: J. Cell Biol., 157, 565-570 (2002)
- ↑ Wang, K.C., et al.: Nature, 420, 72-78 (2002)
- ↑ Yamashita, T., Tucker, K.L., Barde, Y.A.: Neuron, 24: 585-593 (1999)